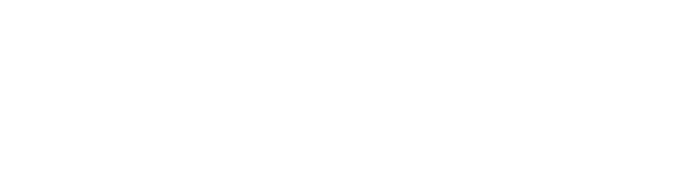大きな動向としては、
①コロナで地価の上昇基調にストップがかかった。
②特に、銀座などインバウンド需要で高騰していた商業地の下落が顕著。
ということでしょうか。
③アフターコロナでは、リモートワークや在宅勤務も企業によってかなり差はあるでしょうけれど、コロナ前に比べればはるかに多く実施、定着するに違いありませんから、オフィス需要は減るはずですし、すでにその兆候はあると言われています。

④インバウンド需要もしばらくは、コロナ以前の水準に戻らないでしょうから、優遇措置もあり急増していたホテル用地の需要も激減するはずです。
ということで、大きくは地価は弱含み。エンドユーザー市場の住宅用不動産価格も下げていくのではないかとの見立てが多いですね。私もメインシナリオはそう見ます。特に、少子高齢化もありますので、地方、郊外は上がる要素の方が少ないですね。
でも、一方で一緒くたに考えない方がよいのが、都心部の特にタワマンに代表される大規模集合住宅です。
本”たんさんタワー”では何度も指摘してきましたが、本気で購入を考えるとすれば週刊誌的な煽り記事の”タワマン暴落”論をあまりアテにしない方が良いと思っています。

7月23日時点での私の記事

9月23日の日経新聞記事

タワマンウオッチャーとしての私の体感値「コロナだけど都心の集合住宅価格はむしろ上がっているし、需要は引き続き堅いな。」というものに日経の記事も一致しています。
それではなぜ、都心部の集合住宅がこんなコロナの状況でも下がらないと言えるかといえば、
①リモートワークが増えれば増えるほど、都市の便利さが重要になる。からです。
在宅勤務といっても一日中狭い自宅で仕事をしていては息が詰まるというものです、近くにカフェがあったり、在宅勤務後はぐらいは街場のレストランに外食したいなというのは自然な感覚です。まして通勤がない分運動不足になりやすいですから、ジムやサウナのニーズはきっと高まります。
(写真:AC)
②リモートワークだからこそ、いざという時ぐらいは出社できる態勢でいたいという感覚もあるのではないでしょうか。特に管理職の方は、リモートワークと背中合わせの危機管理を考えてしまうように思います。
そんな中で、今回の東京基準地価、住宅地下落率が最も高かったのが、大田区田園調布五丁目の3%ダウンも象徴的かと思いますが、”田園都市コンセプト”の数少ない成功例である田園調布、成城学園、浜田山などの一角がすでに崩れ始めたことが象徴しているかと思います。いたるところ都市化がすすむ日本で本当の郊外を求めるのならば、いっそ軽井沢レベルで住居を求めない限り実現しません。つまり軽井沢は地価が上がるでしょうが、世田谷を始めとする私鉄沿線の今まで高く評価されてきた郊外型住宅地は今後はなかなか厳しいように思います。

もちろん都心部のオフィス、ホテル用地が大規模集合住宅向けに転用され始めれば、都心部の集合住宅価格の高止まりにも影響は出てくると思いますが少なくとも5年以上の時間がかかるのではないでしょうか。

それにしても振り返ってつくづく思うのは、都心部は昔から不動産価格がもちろん高かったわけですが、その分どんどんお金をかけたマンション、商業施設、オフィスで開発され続けますね。つまり高額な地価が、それに見合うお金のかかった開発を呼び、それが更に人気を高めるという自己触媒的な循環が生まれやすいですね。
これはアフターコロナも変わらないように思います。
あまり巷では見かけない論調ではあるのですが、働き盛りで東京に住む人は、都心にこだわっていくことでライフスタイルも充実し、結果資産を維持する効果もあるように思いますが、いかがでしょうか?
「大塚家具応援企画」他 秋月涼佑 建築・インテリア 記事一覧へ
記事の更新情報をお届けしています。ぜひフォーローください。
Follow @ryosukeakizuki
facebookはこちらから。