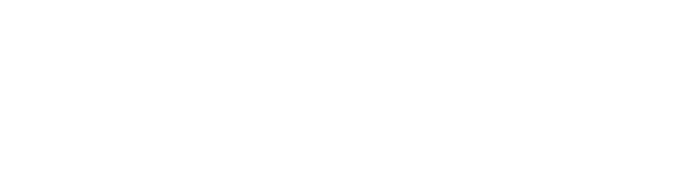私は活字中毒だと思っています。読めるものならばなんでも年から年中読んでいたいといったタイプで、もちろん下世話で恐縮ですがトイレで何か読むのはデフォルトです。未読の本や雑誌がストックしてある家は良いのですが、出先でなんかの拍子に手元に文庫本や新書がないとちょっとしたパニックになって、駅の売店さえ漁ってしまいます。
ネット時代になってそこは便利ですよね。大量に記事を読めるので、昔なら出会えなかったような書き手の記事に往々出会えるのはうれしい限りです。とは言え、ネット記事はやはり読み切りものがメインですので、まとまったものはやはり本で読みたいですね。
音楽音源は大量のCDやレコードの物理メディアをかなり早い段階(10年ほど前?)すべてハイレゾでリッピングして、処分したぐらいですからデジタル化にはまったく抵抗がありませんが、書籍と雑誌は紙で読む方が好きです。
一杯のコーヒーと刷りたての新聞が目の前にある一瞬の幸福感といったら!至福としか言えませんよね。

でも期待値が高すぎるのでしょうか。それが新聞のフォーマルさを保っているのだとは思いますが、公式発表的な食い足りない記事が多いですよね。もちろんオピニオンやエッセー的なうれしい記事もありますが、主に外部の有識者が書くことが多いです。
ずーっと素朴な疑問なのですが、記者さんって、少なくとも書くことが好きで記者になったはずだけど、新聞を裏から見ても表から見ても抑制の効きまくった記事ばかりで、フラストレーションないのかな?といつも不思議なんです。
というのが、日本の新聞社は巨大ですから、記者さんの数も大手各社千人単位だったりしますからね。もちろん毎日あのページ数の記事が埋まるわけですから、それなりに書いてらっしゃるんでしょうけど、記者の数からすればむしろ記事数はすごく少ない気がします。まして、記者の意見を少しでも反映している感じの記事は、論説委員レベルにでもならないと書かせてもらえないのでは?と感じるほどお目にかかりません。
アエラとか新聞社系の雑誌の記事などを見ると流石だな~という記事が多く楽しませてもらえるので、媒体特性の違いではあるのでしょうけれど。何せ、書ける能力があって情報もあるのに書けないというのは拷問のような気がします。

読ませていただく方からすれば、それだけの人的、時間的リソースを投入した上で、そこから高度に濃縮された記事を読ませていただいていると考えればありがたい部分もありますが、余計なお世話ですが記者さんのメンタルは大丈夫なんですかね。
(書くのが好きな人はやはり毎日あれこれ書きたいじゃないですか。私なんか頼まれもしないのに毎日のように、まだまだ野良サイトの「たんさんタワー」に好きでこうやって記事を書き、まだまだすごく多くはないかもしれない方に読んでいただくことを喜びと感じています。まあ引き合いに出すのも申し訳ないのですが。。。)

かく言う私も、広告会社の組織人時代は公にモノを書くのが憚られ(SNSさえ控えていました)、書きたいという気持ちが独立の一方の理由であったのでそのあたりの気持ちはなんとなく分かる気がします。

<写真:司馬遼太郎「ビジネスエリートの新論語」 (文春新書)>
一人の活字好き、新聞好きとして、今度知り合いの記者さんにでも聞いてみようかなと思います。
記事の更新情報をお届けしています。ぜひフォーローください。
Follow @ryosukeakizuki
facebookはこちらから。