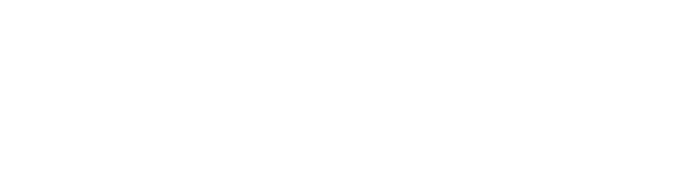もちろん教文館は心の灯火なのですが、いかんせん規模が小さい。有楽町まで歩いて三省堂にいくぐらいですかね。
ネット時代の功罪は色々ありますが、やはり印刷という大きな費用のかかる書籍という形態で読書することはとんでもない贅沢になってしまうのでしょうかねこれからの時代。
音楽については、結構大量に持っていたレコードやCDを処分してハイレゾデータで聴くことにまったく抵抗のない私ですが、本だけはやはり書籍のかたちで読みたいんですよね。もちろん電子書籍も併用していますが、やはり何かが違う。
雑誌なんかも、毎月結構買っていますから、電子版の方が場所も取らないしコストも安いのですが、やはり雑誌は紙が良い。なぜなのでしょうか、やはりグラビア的な要素が大きいからかもしれませんね。手に取って、豊かなビジュアルを見ながら読みたいわけです。
そんな雑誌も随分知らず知らずのうちに減ってしまったように思いますね。
かつては、インテリアや建築の雑誌も結構な数あったのに、新建築は最盛時の厚さの四分の一ですかね。ペラペラです。
インテリア雑誌さえ立ち行かないのは、やはり日本の住まう生活文化のレベルが所詮は低いことを表しているようには思います。

書籍と違って、雑誌ばかりは場所をとるので、さすがに蔵書まではできず(資料的に見返したいときはそれこそ電子データで良いかと)泣く泣く処分していくのですが、I’m home.だけはバックナンバーもしっかり保存しています。

“I’m home.”さんの独自性って、「新建築」など建築家向けの雑誌って内装は理想主義というか、ミニマリズム、モダニズムで「どうだ!カッコ良いだろう!」で終わってしまうのですが、さすが商業施設の内装などを豊富に取り上げてきた商店建築社さんだけあって、現実の生活で使うインテリアであれば当然欲しい、温かみであったり、温もり、ちょっとした素材の質感やテクスチュアなど装飾的要素もチープにならない範囲で正面から取り上げていることなんですよね。



私も基本ミニマリズム大好きなのですが、実生活空間となるとダサくならない範囲で、居心地良さを感じれる要素をインテリアに欲するようになりました。でも日本人ってそういうの苦手なんですよね。ミニマリズムまではできても、ちょっと空間に何かを付加していくと途端にひたすらダサかったり、取り留めのない空間になりがちです。
“I’m home.”のインテリアには、あえての色使いや装飾的なモチーフ使いなど、我々が苦手な要素に対してのインスピレーションが豊富なんです。そこら辺が傑出したところだと思っています。



そんな、この雑誌ならではのセンスで実際のインテリアプランニングをしていて、モダンでありながら無味乾燥にならない絶妙な匙加減が本当に素晴らしい。やっぱりセンスさえ良ければ、日本でも相当良い空間を実現できると確信する次第です。



記事の更新情報をお届けしています。ぜひフォーローください。
Follow @ryosukeakizuki
facebookはこちらから。