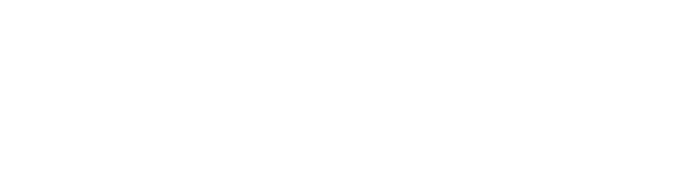下記記事によれば、それなりの交渉が水面下で進んでいたというわけですね。

それにしてもあらためて東京ドームが立地する「水道橋」という立地は本当に興味深い。
第1に、そもそも東京山手線のど真ん中のような立地です。
それゆえか、JR、東京メトロ丸ノ内線、南北線、都営三田線となんと4路線に囲まれた立地で無茶苦茶鉄道アクセスが良いんですよね。
むしろ東京ドームという特殊な空間がそれぞれの路線相互の行き来を邪魔していたような感さえあります。
この土地が再開発されて、もう少し有機的に結節されればかなり便利な立地です。
第2に、文京区という立地です。
江戸以来栄え、今や東大他伝統校が多数立地する文教地域でもあり、大和郷など成金ではない本当の富裕層も住んでいる土地です。
しかも後楽園、小石川植物園と「地位(ちぐらい)」が徳川家由来の考えてみればこれほど高い場所もないですよね。
冒頭の東洋経済オンラインの記事で、開発が進まなかった理由が「都市計画公園」指定にあったということを聞きなるほどなと理解しましたが、
これほどのポテンシャルの立地が再開発されず、後楽園球場からドーム、後楽園遊園地、黄色ビル、近年では東京ドームホテルなどの開発はあったものの真ん中に巨大な構造物があるゆえにあまり有機的な動線もなく、特に魅力的なエリアではありませんでした。
確かにここは三井不動産のノウハウで、本格的な再開発が行われればスゴイことになることは間違いありません。
私が、この件で興味を持っているのは、
東京には南北問題があります。中央・総武線で区切られた北半球。文京区、山手線内側の新宿区、豊島区(サンシャイン除く)はまさに伝統的なエリアであるだけに、超高層ビルやタワマンの開発が難しく意外と密度が低い状況が続いてきたわけです。要は地元がウルサ型ということです。
(写真:AC)
私のように、平均的な共働き世帯にこそ超高層集合住宅の供給が不可欠と考える論者からすると、まさに既得権の巣窟。
タワマンをガンガン受け入れる、湾岸や新宿(山手線外側)、池袋の副都心とそこはまったく違います。
多分あと2,3世代変わらないと文京区を中心とする東京の山手線内側北半球は変わらないなかなと思ってきましたが、文京区役所にも隣接する東京ドームの開発が実現すればこの雰囲気も少し変わるのではないでしょうか。
もちろん私とて、古き良き東京。江戸の情緒を残す東京は大好きなのですが。それと同じくらい、東京都心でも平均的な収入でも100㎡以上、少しがんばれば200㎡の広さの集合住宅に住める環境が実現すれば良いなと思ってきました。
そのためには物理的にタワマンの供給が不可欠なわけですが、現状文京区にそんな物件はあり得ません。
それがゆえ、まさに東京の南北問題解決の起点となるのか?という視点で注目しているわけです。
記事の更新情報をお届けしています。ぜひフォーローください。
秋月涼佑のtwitter
Follow @ryosukeakizuki
facebookはこちらから。