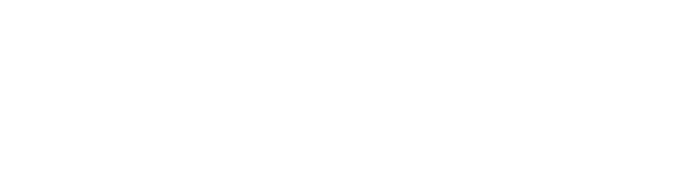実は最近電気自動車(EV)のことが無茶苦茶気になります。
産業論としても、今やほとんど自動車産業一本足打法の日本経済将来に直結する話ですし、もちろん一人の自動車好きとしてもすごく関心をもっています。

じゃあ、アメリカのようにソフトや世界市場を相手にするサービスで勝負できるかと言えば、それこそお寒い限りで、まったく道筋さえ見えてきません。
やはり、モノづくりの強みをワンチャン維持できなければ、日本の成長戦略はどうやっても描けないように思います。
となれば、せめて外国勢が真似できない内燃機関、エンジンの積み上げてきたクリーン化技術や、優位性のありそうな燃料電池(FCV)を自動車の環境対応のメインシナリオにできた方が良いなと考えていました=豊田章男社長と同様の考えをしてきたわけです。
が、もはや中国や欧州にガンガンEV化宣言をぶち上げられて、挙句の果てには日本のポピュリズム化した政治家にまで続々EV宣言するに至り政治的な勝負はつけられてしまったように思います。新型コロナウイルス対策の迷走を見ればわかるように、もはや日本のトップリーダーに科学的、合理的マインドをもって国をリードできる人は皆無のようです。もちろん発電のほとんどを化石燃料に頼る日本において100%電気自動車化が、発電行程を含めての低環境負荷につながるわけもありません。
SankeiBizにも書きましたが、エンジンという油まみれで騒騒しく武骨な存在(まあ、私などクルマ好きはそこが大好きなのですが)、それがないだけでこれほどに別モノに感じるのかというほど、自動車製品というよりもやはり電気製品に近いようなプロダクトとしての完成度を感じてしまったのです。
やはり蒸気機関車と新幹線は違います。ガラケーとスマホも違います。
そんな違いさえ感じてしまったのです。


そしてよくよく考えると、何よりEVの強みは実はクルマ自体というよりも、充電インフラの構築しやすさにあるのではないかとも思うに至りました。
今やガソリンスタンドは冬の時代、若者の自動車離れやそもそも自動車の燃費効率の飛躍的向上もあって、その数はピーク時の三分の一程度のはずです。もちろん今後はますます減るでしょう。最近ではちょっと地方に出ると、ガソリンスタンドがなくて困るようなこともチラホラ感じるようになりました。
その点、今は充電スポットの少なさが不便さの代名詞の電気自動車はこれからいくらでも作り放題。法規的にもハードルが高いガソリンスタンド設置よりはるかに気軽に設置できます。
EVが普及してくれば、商業施設やレジャー施設はこぞって充電スポットを整備するに違いありません。なぜなら、充電スポットほど良い集客設備もそうありません。クルマで来店・来場してくれて、しかも一定時間必ずお店に滞留してくれます。モノを買います、レストランを利用しますと宣言してくれているようなものです。
これは時代が明らかに変わりますね。そこら中に充電スポットがあふれる時代がもうついそこまで来ているように思います。
生活者にとっては選択肢が増える話ですが、肝心なのは日本の最後の砦、自動車メーカーがEVでも世界的競争力を維持してくれることであります。
記事の更新情報をお届けしています。ぜひフォーローください。
Follow @ryosukeakizuki
facebookはこちらから。