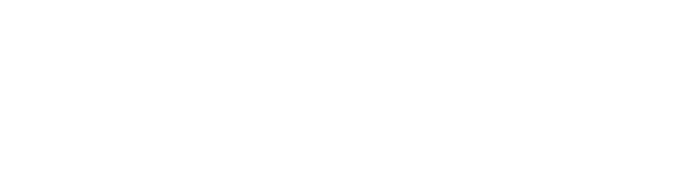小学生の我が子に日本の歴史を教えています。
小学生向けとは言え、自分でも曖昧になっていた日本史の学びなおしの良い機会になっています。
「応仁の乱」前と後で、日本の歴史には大きな分断があるというお話もあるようですが、
つくづく現代日本人の意識にも各時代からの脈々と連なる様々が影響を与えているもんだな、とむしろビックりしています。
「和を以て貴しとなす」の聖徳太子「十七条の憲法」は、さすがお札の絵柄になるくらいですものね、いかにも日本人的な意思決定の在り方を示していて今をもって影響を与えていると思います。
江戸時代、大名や旗本が登城して謹厳に仕事をするイメージなど、なかなかリモートワークが完全には定着しない日本人の働き方感の良くも悪くも原風景になっている気がしたりします。
鴨長明の時代もまた、非常に戦乱や流行り病の困難な時代だったそうです。先が見えない時代の無常観、
「行く川のながれは絶えずして、しかも本の水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて久しくとゞまることなし。世の中にある人とすみかと、またかくの如し。」という普遍的な人間観に死生観が、ああどんな時代も人間は悩みながら過ごしてきたのだなと、やはり共感を誘うのです。

そんな「方丈記」でもう一つ着目する部分と言えば、まさに「方丈」つまり「一丈四方」ですから3mx3mの庵での生活記であるわけですよね。
(写真:wikipediaより、京都下鴨神社)
四畳半に毛が生えたぐらいの広さのミニマムスペースです。そんな極小かつモノも持たない生活の中から、厳しい時代をしのぐ災厄に対し、人間性を失わずにどうしのぐかという、避難、回避の書でもあるわけです。「方丈記」が災害文学と言われるゆえんでもあります。
その後の茶室文化にもつながる、狭いから精神的には貧しくなると必ずしも言えないという考え方が通底しています。
他にも日本には「人は座って半畳、寝て一畳」という言葉もあるぐらいです。
と書きながら矛盾するようなのですが、筆者自身は、それはすごく共感なのだけど、いくらなんでもいつまでもウサギ小屋暮らしが変わらないのもどうなのよ?と思っても同時にいます。個人的には日本人の生活空間の狭さにちょっとアンビバレントではあるのです。

そんな日本人の狭くてもいいや指向の理由は、ざっと考えても
1)都市型の比較的密集地に住むことが好き (歴史的にも田舎は農水産業で苦労が多かったことも影響)
2)普請好きで、すぐ新築したがるので、住宅がストック化しづらく高コスト
3)「方丈記」以来の狭くても貧しくないという精神性
など、色々背景があるように思います。
少なくとも欧米的価値観で、一概に悪いとは言えないはずではあります。
あくまで数十年単位での中期トレンドのお話ではありますが。すでに、失われた20年で、日本人の居住空間は拡大方向から反転縮小傾向だったわけですから、その速度が加速するに過ぎません。


何せ、韓国映画「パラサイト」のような、誰にとっても幸せではない貧富のヒエラルキーが極端な社会にだけはなって欲しくないなと、心から願うところではあります。
記事の更新情報をお届けしています。ぜひフォーローください。
Follow @ryosukeakizuki
facebookはこちらから。