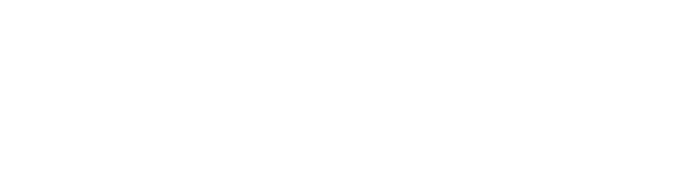これは知りませんでした。なんと国が不動産での「残価設定型」ローンの国策推進を検討しているとのこと。
国土交通省は、「残価設定型」のローンの普及に向け、2021年度にも民間の金融機関が参加するモデル事業を始めると発表した。これにより、資産性がある住宅は返済負担が小さくなるので、家計に優しく、その分、消費が活性する可能性が高い。ここが、国策の最大の狙い目になる。
なるほど、1億円の不動産も8千万円の残価が設定されれば、2千万円の支払いに対するローン設定で済みますものね。
もちろん設定期間を経ても所有したければ、その残価8千万円を支払うとか、再度ローンを設定しなければならないでしょうから、不動産の購入所有と賃貸の中間的なイメージでしょうか。

国策の残化設定型住宅ローンは、資産性がある不動産には適用されるが、資産性がない不動産には適用されることはないだろう。
この意味で、戸建よりマンションのほうが、地方より都市部のほうが、向いていることは明らかだ。価格変動幅が小さく安定しているので、計算しやすいためである。戸建や地方では、マンションより中古市場での取引量が少ないだけに、次の買い手を見つけるのが難しいという現実がある。つまり、こうした場合は施工会社(上記の新生銀行の場合は旭化成ホームズ)の買い取りという条件が必要になる。
事業者の買い取りを伴うようでは、ローン商品の魅力がないことは説明してきた。結局のところ、残化設定型住宅ローンは資産性がある不動産だけに適用される商品ということになるのだ。
こうなると、より都市部に住むことが住居費を下げるコツになり、人口減少している日本ではコンパクトシティ化を推進することにもなる。
なるほど、納得の記事ですよね。恐らく「残価設定」不動産ローンがポピュラーになるとすれば都心部の恐らく大規模集合住宅、典型的にはタワマンとなることでしょう。
そうなると、東京都心部などでもタワマンの供給が増える方向へのダイナミズムがまた動き出すかもしれません。
現在、東京都心部は湾岸地域含めてタワマンの供給量は必ずしも多くありません。
大規模集合住宅に適した用地が少なくなっていることもあります。例えば、大崎、豊洲、東雲などは大きな工場の跡地でしたが、そういった用地も都心周辺には少なくなりました。
(写真:AC)
私が何より残念なのは、住民感情の反対意見で大規模集合住宅が建てにくくなっている現状です。
そうなればマンションの一次取得者層だけでなく、従来ならば100㎡を検討したいた人も「残価設定ローン」で200㎡を検討できるなど、日本人もそれなりの水準の住居の選択ができる時代になれば良いと思いますので、しばらく関心をもってウオッチしていきたいと思います。

記事の更新情報をお届けしています。ぜひフォーローください。
Follow @ryosukeakizuki
facebookはこちらから。