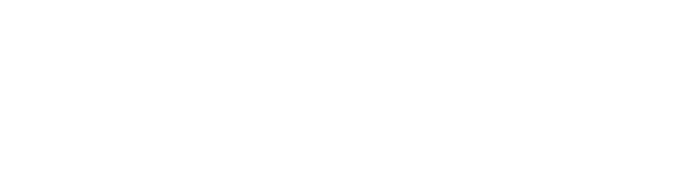私自身そうなのですが、乗り物の話にはどうしても興味がいきます。
いわゆる”関与度”の高い心理状態だということは、自覚があります。
今朝から掲載のTOKYO BRTの記事も、東京ローカルのネタなので厳しいかなと思いつつ、結構読んでいただいているようです。

いわゆる”関与度”の高い心理状態だということは、自覚があります。
今朝から掲載のTOKYO BRTの記事も、東京ローカルのネタなので厳しいかなと思いつつ、結構読んでいただいているようです。
SankeiBiz(サンケイビズ):自分を磨く経済情報サイト
SankeiBiz(サンケイビズ)は産経新聞グループの経済情報サイトです。「仕事・キャリア」「自分磨き」を主なテーマに、ニュースはもちろん、気鋭の経営者や識者が執筆する連載・コラムなどビジネスパーソンの知的好奇心を満たすコンテンツをご覧ください。
なぜ我々は”乗り物”に格段の興味をもってしまうのか?
色々なファクターがあるかと思いますが、
仮説1)人間を個体単体では実現不可能なほど、速く、遠くまで運んでくれるものだから。
その特性は、やはり”スポーツ”という概念にも結びつきが強いですし、速さを追求してしまうマインドも自然に発生してきます。

その特性は、やはり”スポーツ”という概念にも結びつきが強いですし、速さを追求してしまうマインドも自然に発生してきます。
301 Moved Permanently
仮説2)人間が作る、もっとも気合の入ったプロダクトだから。
そんな高機能な機械である”乗り物”は、人類叡智の結晶です。乗用車だって、家を除けば生涯で個人最大の買い物に違いありません。そんなストレートな”モノ”としてのすごさに我々は惹かれるのではないでしょうか。
仮説3)インフラとしての重要性
やはり、インフラ=国力とニアリーイコールだと痛感します。
日本も、振り返れば大変なインフラ大国だと思います。広大過ぎず、狭すぎないこの国土の適度な大きさが、効率的なインフラ整備を可能にしていてラッキー過ぎると思っています。少々やり過ぎのクオリティの道路インフラなど、どこの国と比べてもそん色ないレベルです。
でも、数十年後に人口が半減するという日本。今までのノリで、最高スペックで大量にインフラ整備していて良いとは思えません。交通インフラも適度なダウンサイジングの発想があって良いようには思います。
たかがバス。ある意味”乗り物”界で一番、ダサくて、ショボいヤツと見下されていたように思いますが、
BRTの取り組みは、そんなバスに対する認識自体を変えることができるか?
という、これからの日本人のライフスタイル。人口がどんどん減っていく社会のインフラ観を問う試金石のように思います。
そんな視点で書いた記事です。ぜひご一読いただければと思います。

SankeiBiz(サンケイビズ):自分を磨く経済情報サイト
SankeiBiz(サンケイビズ)は産経新聞グループの経済情報サイトです。「仕事・キャリア」「自分磨き」を主なテーマに、ニュースはもちろん、気鋭の経営者や識者が執筆する連載・コラムなどビジネスパーソンの知的好奇心を満たすコンテンツをご覧ください。
記事の更新情報をお届けしています。ぜひフォーローください。
秋月涼佑のtwitter
Follow @ryosukeakizuki
facebookはこちらから。