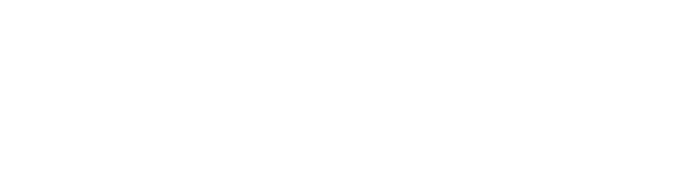人間って結構鈍感で頑丈にできているなあといつも思います。ちょっとやそっとのことでは死なない。
もちろん反面、打ち所が悪ければ的なこともあって死んじゃうときはあっけないとも言えるのでしょうが、これを書いている私も読んでくださっている方も幸い今のところは生きています。
あるお医者さんの先生が、無菌状態ほど悪いものはないから、積極的に落ちたものを食べたり、人の使った直後のトイレで用を足したりするというようなことを書いていて、結構はっとさせられました。
みなさん、私たちを守ってくれるバイ菌を大切にしないと、免疫力が落ちて、風邪を引きやすくなったり、アレルギー疾患を発症したりしますよ。僕みたいに年をとってくると、守ってくれるバイ菌も少なくなりますから、若者がトイレ個室から出てくるのを見つけると、まだ便座に菌がついている温かいうちにサッと座って『菌をくれて、ありがとう』と喜びます
ということであれば、ちょっとやそっと汚かろうがなんだろうが、あまり潔癖症になってはいけないのでしょうが、やはりコロナの時代はなかなか気になってしまうのもまた事実です。特に、我々が24時間365日吸ったり吐いたりする生活空間の空気については基本キレイであればあるほど良いのではないでしょうか?
でも、空気というものは目に見えないものだけに、なかなか対処しにくいというのが現実です。ちなみに一般的なエアコンは今ある空気を温めたり冷やしたりしますが、基本換気はしない仕組みです。全熱交換型という高級なタイプでは換気もするのでしょうが、古いビルや一般家庭のエアコンはほとんど換気をしないタイプと考えて間違いがないはずです。すると何が起きるかというと、このコロナの時代に思いっきり淀んだ空気の中を我々は生活することになるわけです。

例えば、個人タクシーさん。かなり年配のまさに個のオーラを発散しまくっている運転手さんに限って、強烈に低い温度で内気循環させて万全の体制でお客を迎えてくださる。こんなとき申し訳ないながらも温度上げてとお願いした上で、窓を開けさせてもらうと非常にイヤな顔をされます。
あれは、風水的な何かがあるのでしょうか?海外でも往々、本格的な中華料理屋さんになればなるほど嵌め殺しのピクチャーウインドーの中の空気を絶対に入れ替えませんという固い意志を感じさせるお店が多かったりもします。

でもうれしいのは、ようやく最近オープンテラスのカフェやレストランがリアルに増えてきたことです。一昔前は、建築家がテラス席を用意していても店長やマネージャーが往々「外気は悪、なるべく閉め切ってエアコンを効かせる」派の方で運用上テラス席を廃止するケースが多く、「テラス席使っても良いですか?」と聞くと、こいつキ〇〇イか?という反応をされたものです。
ましてアフターコロナの時代は、きっと外気に対する意識がグッと高まると思います。
早速、今朝の日経新聞で建築家の隈研吾氏が、「アフターコロナは箱から出る時代」とインタビューに答えていました。
――都市のイメージが大きく変わりそうですね。
「都市のイメージが変わったらいいんじゃないかな。地方と都市の境目みたいなのも薄らいでいく。都市とそれ以外がはっきり違う領域ではなくて、同じ空間として定義される感じかな。人間が歩く道の中でいろんな生活が繰り広げられる。仕事する場所でもあるし、食べる場所でもある」
「(中世期の)ペストの後、道路がぐちゃぐちゃで汚いから、みんな箱の中に生活の場所を求めたのが14世紀。それ以前から人間は箱の中に入りたがっていたとも言えると思うんだよね。『箱に入ると幸せだ』という幻想がある種、人間を支配していた」
「それがペストの後さらに強まって、ルネサンス建築が生まれて箱がどんどん大きくなってきて最終的に超高層建築という20世紀のアメリカが作ったスタイルに行き着く。
「そういう一直線の流れが折り返し点に来て、『箱から出よう』というふうにこれからなる気がするな。やっぱり大きな歴史の折り返し点だと思っていますね。直感的に『箱の中に人間は多分いられないな』と感じています。箱の中を空調するために、ものすごいエネルギーを使って箱の外に熱を出して、箱の外はどんどん悪くなる。そういう悪循環が起きていたから、なんか直感的に『これはもたないんじゃないか』って気はしてました」
「日本の昔の建築は箱の中か外かわからない作り方をしていました。ひさしを出すという作り方は箱の外の空間にあまり悪いものを出さないし、全体として穏やかな空間を作っているわけです。ああいう作り方をもう一回呼び戻さなきゃいけないなと思いますね。風が穏やかに流れていく感じを科学的に研究する。この方向に向かっていく気がします」
「これまでは箱をどういうふうにきれいに飾り立てるか、そっちにしかお金が向かってなくて建築がある意味で退化していたと僕は思いますね。超高層ビルという形式が20世紀にできてから、あとは超高層をお化粧し、どうやって高級そうにみせるかだけを考えて、その先を考えてこなかった。これは退化だったし、怠慢だったと思う。建築の世界、都市計画の世界、みんな怠慢だったと思う。みんな自分たちの怠慢さに気づいて新しい方向に向かって知恵を絞らないと。技術者もデザイナーも力を合わせていかないといけない」
さすが、売れっ子建築家にして文明論的な論考にも定評がある隈先生。
私自身も、穏やかな風を感じられる空間で仕事をし、食事をし、くつろぎ団らんするライフスタイルをさらに追求していきたいと意を強くした次第です。
建築・インテリア過去記事一覧へ
記事の更新情報をお届けしています。ぜひフォーローください。
Follow @ryosukeakizuki
facebookはこちらから。