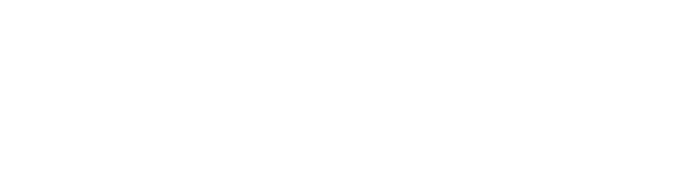先回、言葉の問題だけとっても、外国語で仕事をするということは想像以上に厳しいことですよ。ということに触れました。

今回は、働き方・企業文化の問題です。
本当に日本というのは稀有な国でやってきたと思います。
私が日本人の生活にとってという意味ですごく良かったと思うのは、「八百万(やおよろず)の神々」つまり一神教の偏狭さにとらわれない世俗的な宗教観です。
でも働き方という意味では、圧倒的平等社会が日本の会社だということではないでしょうか?
良く日本の社会を「もっとも成功した社会主義」という言い方をしますが、それを実現させたのが日本企業の独特のあり方でしたよね。
つまり資本において、中立性が高く、オーナーにしばられにくい。今は随分解消されましたが、かつての大企業の主な株主は銀行や企業間の持ち合いでした。
なぜ日本企業が個人のオーナーシップから独立する傾向にあったかと言えば、ひとつは強烈な相続税でオーナー家が少なくとも資本面では影響力を保ち続けられないから。(最近でも、朝日新聞社の著名なオーナー家だった村山家が実質的に相続で相当の株を手放して話題になりました関連記事)
もう一つは、太平洋戦争の敗戦も大きかったのではないでしょうか。財閥解体をはじめ、それまでの重鎮が帰ってこず若い層にガラッと変わったりで、ここで戦前からの企業は会社の在り方が随分変わりました。(電通中興の祖、吉田秀雄が活躍した背景もこういった部分です、)
だから、ほとんどの大企業で新卒で一斉にがんばったら誰にでも一応社長になれるチャンスがある(もちろんフラッグが新人時代から立っていたり、現実には出世コースと一般人で人事が分かれていたりするケースもありますが、それも含めて競争の範囲ですかね。)という、結構奇跡的な会社の有り様が成立していたわけです。実際に社長と平社員の給与の差も、諸外国に比べれば圧倒的に低いのが日本社会ですからね。まさに「成功した社会主義」と言えたわけです。
よく会社は誰のためにあるか?と言われて、世界の資本主義社会の標準解は「株主」となるのでしょうが、資本に色がない日本企業では「社員」という答えで嘘じゃない会社がたくさんあります。(例えば、広告代理店なんてまさにそうですよ。電通、博報堂ともに誰も株主のことなんか気にしていません。ADKにいたっては一度は外資を入れましたが、嫌って株を買い戻してしまいました)
そんな「釣りバカ日誌」のように、社長も社員も家族、仲間で平等に穏やかにやってきた日本の会社社会ですが、グローバルスタンダードの資本主義はジャングルの法則です。厳しい現実が待っていると思いますね。
カジノを見ていると、外国企業の組織のありかたが良く分かります。
DanMSchellによるPixabayからの画像
ディーラーがいて、そのディーラーをピットボス(カジノテーブル何台かを監視するマネージャー)が監視している。そのピットボスをアイインザスカイつまりカメラで誰かが監視している。その監視役をカジノ会社のマネージャーが管理し、雇われ社長が上で見ている。でもその雇われ社長もオーナーに年単位で評価されダメなら速攻で首が飛ぶ。やっかいなのはそのオーナーのバックに金主がいたりすることで、どこまでいっても徹底した資本の理論で厳しい社会です。
つまり一部の大資本家はまさにブルジョワジーで絶対的権力と自由を持つ。雇われ社長階層は奴隷頭役で、一見待遇が良いけど使い捨て。はっきりいてその他大多数は使用人です。
もちろん、新興のIT企業などでストックオプション等を付与して、社員のエンゲージメントを高める工夫は随所にあるものの、基本は使用人はダメなら首!の世界ですからね。厳しいもんです。法制度の違う日本では簡単に社員を首にはできないはずですが、日本の外資でも平均勤続年数も総じて長くはないのはご存知の通りです。
世の中的に外資系と言えば、きらびやかで先進的なイメージがあるかと思いますが、平均的な日本人にとっては厳しく感じる企業文化の会社が多いのではないかなと思います。まして会社が中華系資本に買い取られるとどういう運営になるのかはちょっと想像さえできません。
コロナウイルスは第二波もきっとあるでしょうが、日本人にとって感染のリスクは限定的であることが第一波で証明されました。
経済のダメージは、長期にわたって多くの人が深刻な影響を受けるという意味で、感染症のリスクより低いとは絶対言えません。次こそは、なんとか冷静な判断をしていきたいものだとつくづく思うところです。
記事の更新情報をお届けしています。ぜひフォーローください。
秋月涼佑のtwitter
Follow @ryosukeakizuki
facebookはこちらから。記事の更新情報をお届けしています。ぜひフォーローください。