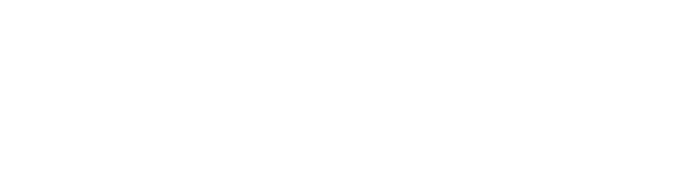というわけで、新型コロナウイルス流行対策というわけで、一日仕事から何から家でやっているわけですが、軽く音楽をあてて気分転換したくなる瞬間も多いですね。

Amazonのハイレゾストリーミング開始に負けじと、緊急に立ち上げた当初に比べてインターフェースが着々と整備されていくのもうれしいところです。
さて、ストリーミングサービスの恩恵で、ありとあらゆるジャンルの音楽が聴き放題なわけで、これ幸いとなんでも聴くのですが、ハイレゾならではクラシックも聴きごたえがあります。例えば、オーケストラ楽曲など、ピアニシモとフォルテシモのサウンドダイナミズムが感じられたり、コンサート会場のような繊細さややわらかさを感じられることにハイレゾの醍醐味が大きいですよね。
なのですが、実はクラシックの音源では96kHz/24bit以上でハイレゾ供給されているものはまだまだ限られます。まあ恐らく時間とともに増えていくのでしょうけれど。
そんな中で、さすがソニー(ユニーバサルさんの音源ですが)と言うべきでしょうか、カラヤンのオムニバス盤は一番最初から96kHz/24bitのハイレゾ音源が提供されています。
ヘルベルト・フォン・カラヤンと言えば、あまりにも有名。帝王と呼ばれ、ルックスが良くて、奥さん美人で、飛行機とかポルシェに颯爽と乗ってなど、私のようなクラシック半可通からすると逆にどうせミーハーなスターなんでしょうなどと、ちゃんと聴いたこともないのに勝手に生意気な印象を持ったりしていました。
まして、ラデッキー行進曲などのアンコールにかかるような名曲選ともなれば、普段ラフマニノフの協奏曲がとかうそぶいている私には、ちょっと子供だましだろなどと勝手に舐めておりました。
いやーお恥ずかし話です。
なんでも帝王カラヤンは、小品にこそ丁寧さと完璧さを注入することにこだわったとの逸話をあとで知りました。
まさにこのアルバムを聴くと、その言葉の真意を理解することができ脱帽する他ありません。
その音響面での美しさを追求する姿勢から「音楽のセールスマン」などと当時揶揄されたとのことですが、いやこのハイレゾならでは感じられる音のきらびやかさ、精緻さに魅了されない人はいないはずです。まさにダイナミックにして緻密。
どの曲も良く知られた曲ばかりですが、カラヤンの解釈を聴いてしまうと、他のテンポや解釈が異端と思えてしまうほどの完成度とバランス。
やはり”完璧”という言葉が、一番近い表現のように思います。
特に、ハイレゾ向きと感じるのは最後の曲。『歌劇《イーゴリ公》: ダッタン人の踊り』です。
みんなが聴いたことことがある、情緒的でエレガントなメロディと後半迫力のパーカッションの大胆さが凄く印象的です。ハイレゾならではこの弱と強のコントラストが迫ってきます。
録音してから50年近くたっていても音質も一級品。
日本の高度成長期、ソニーが世界有数の音響機器メーカーとして認められる上で、カラヤンとのパートナーシップが大きく貢献したことは有名ですが、そんな日本人にとっても敬愛すべき”帝王”の偉大さを今さらですが、知ることができるのもハイレゾの恩恵。トラは死して皮を残すというと変かもしれませんが、とにかく再発見の喜びに浸れる一枚のように思えてなりません。

【ハイレゾで聴くカラヤン・ベスト ヘルベルト・フォン・カラヤン】
96kHz/24bit
1交響詩《ツァラトゥストラはかく語りき》 作品30: 導入部
2組曲《惑星》 作品32: 木星―喜悦をもたらす者
3管弦楽組曲 第2番 BWV1067: 第7曲: Badinerie
4リュートのための古代舞曲とアリア 第3組曲: 第3曲: シチリアーナ
5ラデツキー行進曲 作品228
6交響詩《ドン・ファン》作品20
7交響曲 第2番 ニ長調 作品73: 第3楽章: Allegretto grazioso ( Quasi andantino) – Presto ma non assai
8歌劇《マドンナの宝石》: 第3幕間奏曲
9常動曲 作品257
10弦楽のための協奏曲 ト長調 RV151 《コンチェルト・ア・ラ・ルスティカ(田園風)》: 第1楽章: Presto
11セレナード 第13番 ト長調 K.525 《アイネ・クライネ・ナハトムジーク》: 第1楽章: Allegro
124つの最後の歌: 第1曲: 春
13歌劇《イーゴリ公》: ダッタン人の踊り
音楽・オーディオ関連過去記事一覧へ
記事の更新情報をお届けしています。ぜひフォーローください。
Follow @ryosukeakizuki
facebookはこちらから。